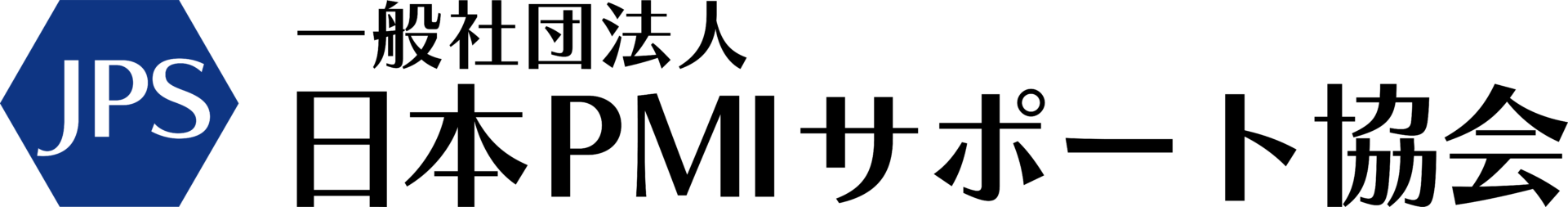はじめに
M&A後の統合プロセス(PMI)において、シナジー創出の計画は描いたものの、現場が混乱・疲弊し、計画が全く進まない。そんな悩みを抱えていませんか。異なる企業文化と業務プロセスが混在し、非効率が蔓延。この状況を放置すれば、社員の士気は著しく低下し、M&Aそのものが「失敗」の烙印を押されかねません。本記事では、PMI成功の鍵となる「業務改善」の重要性を解説し、現場の当事者意識を引き出すことで組織を活性化させる、具体的な手法を提示します。
なぜPMIで現場は疲弊するのか?シナジーを阻む3つの壁
M&A後の統合局面では、短期間での異動、退職、そして業務統合が嵐のように訪れます。この変革の渦中で、多くの企業が共通の課題に直面します。それは、現場レベルでの深刻な疲弊です。なぜ、あれほど期待を込めてスタートしたはずのPMIで、現場は疲弊してしまうのでしょうか。その背景には、避けては通れない3つの壁が存在します。
業務プロセスの「ブラックボックス化」
買収元と被買収企業、それぞれが長年培ってきた業務プロセスが混在し、互いの業務の全体像が見えなくなる。これが「ブラックボックス化」の正体です。日々の業務に追われる中で、「誰が、何を、どのように行っているのか」を把握する余裕はありません。この不透明な状態が、業務の重複や属人化といった非効率を生み、シナジー創出に向けた改善の第一歩を、見えない壁のように阻むのです。
「慣れ」が引き起こす改善意識の欠如
「このやり方が、昔からの当たり前だから」。多くの社員にとって、自らの業務は疑う余地のない、慣れ親しんだ作業です。そのため、そこに潜む非効率や無駄なストレスポイントに、自分自身で気づくことは極めて困難です。先日、我々が支援した企業のワークショップでも「慣れた自分の業務の改善点の発見は難しい」という声が聞かれました。この「慣れ」という壁が、改善の必要性そのものを認識させなくしてしまうのです。
変化に対する「受け身」の姿勢
PMIはトップダウンで進められる性質上、現場社員はどうしても「やらされ感」を抱きがちになります。新しい組織への期待よりも、自らの仕事や役割が変わることへの不安が先行してしまうのです。この受け身の姿勢は、シナジー創出という本来の目的に向けた、主体的で前向きな行動を抑制します。「どうせ上が決めることだから」という諦めムードが蔓延すれば、組織の活力は失われていく一方です。
現場を主役にする業務改善PMI 3つの解決策
シナジーを阻む3つの壁を乗り越え、現場の力を最大限に引き出す。そのための最も有効な処方箋が、「現場主導の業務改善」です。トップダウンの号令ではなく、現場が自ら課題を見つけ、解決策を考え、実行する。このプロセスを仕組み化することが、PMIを成功へと導きます。
「業務の棚卸し」による徹底的な可視化
まず取り組むべきは、全ての業務を洗い出し、誰が、何を、どのように行っているかを客観的に可視化することです。これは単なる作業リストの作成ではありません。業務フロー図などを用いて、プロセス全体の流れ、各工程にかかる時間、そしてボトルネックとなっている箇所を明確にする、いわば「組織の健康診断」です。このステップにより、これまで感覚的にしか捉えられていなかった問題点が、具体的な改善ターゲットとして浮かび上がります。
外部ファシリテーターによる「客観的視点」の注入
「自分たちの業務の当たり前」を打ち破るには、外部の視点が極めて有効です。先日、当協会のパートナーコンサルタントである小池がファシリテーターを務めたワークショップでも、「別のところから意見をもらうことで多くの気づきを得られた」という感想をいただきました。PMIと業務改善に精通した第三者が介在することで、参加者は心理的な安全性を確保された場で本音を語り、議論を深め、自分たちだけでは決して至らなかったであろう改善の糸口を発見できるのです。
「全員参加のワークショップ」による当事者意識の醸成
改善策をコンサルタントが作り、トップダウンで押し付ける手法では、現場の「やらされ感」は払拭できません。重要なのは、現場社員が主役となるワークショップ形式で議論を進めることです。「業務棚卸→ストレスポイントの把握→業務フローの可視化→改善アイデアの議論→PDCA」。この一連のステップをチームで体験し、自らの手で改善策を創り出すプロセスを通じて、「受け身」の姿勢は「自分ごと」としての当事者意識へと劇的に変化します。
成功の鍵を握る各階層の役割
現場主導の業務改善を成功させるには、組織の各階層がそれぞれの役割を正しく認識し、全社一丸となって取り組む姿勢が不可欠です。経営層、PMI担当者、そして現場、それぞれの立場から何をすべきかを解説します。
経営層の役割
業務改善を単なるコスト削減活動としてではなく、社員の成長と組織活性化のための重要な「未来への投資」であると位置づけることが全ての出発点です。そして、現場へ大胆に権限を委譲し、ワークショップのような「対話の場」を公式に設定してください。経営陣がその重要性を理解し、本気で支援する姿勢を示すことが、現場の勇気と主体性を引き出します。
責任者(PMI担当)の役割
経営のビジョンと現場の現実を結ぶ、極めて重要な架け橋です。ワークショップの企画・運営はもちろんのこと、そこで生まれた改善アイデアが絵に描いた餅で終わらぬよう、部署間の調整や必要なリソースの確保に奔走します。現場から生まれた小さな成功(Quick Win)を積極的に称賛し、その成功体験を全社に展開していくことで、改善の機運を大きなうねりへと変えていく役割を担います。
現場の役割
日々の業務をただ繰り返すのではなく、「会社の主役は自分たちである」という意識を持つことが何よりも重要です。自分の仕事を「当たり前」と捉えず、常により良い方法はないかと問い続ける探求心が求められます。ワークショップの場では、役職や経験にとらわれず、率直に意見を出し合い、他者の意見に真摯に耳を傾ける。その姿勢こそが、個人の成長とチーム全体の進化に直結します。
結論:PMIのエンジンは、輝き始めた「現場の目」にある
M&A後のPMIを成功に導く鍵は、壮大な戦略や最新のITシステムだけではありません。その核心は、現場を徹底的に巻き込んだ「業務改善」にあります。
業務を可視化し、客観的な視点を取り入れ、全員参加で議論を尽くす。
このプロセスを通じて、当初は変化に戸惑い、受け身だった現場社員の目が、徐々に輝きを放ち始めます。自らの想いを知り、現状を客観的に把握し、仲間と直接意見を交わす。その瞬間に生まれる「当事者意識」こそが、PMIという困難な航海を前に進める、最も力強いエンジンとなるのです。
もし貴社のPMIが、現場の混乱や疲弊によって停滞しているのなら、我々、一般社団法人日本PMIサポート協会にご相談ください。専門家による「業務改善ワークショップ」が、貴社の変革の、確かな第一歩をサポートします。
→ 無料相談・お問い合わせはこちらから https://pmi-support.jp/contact/