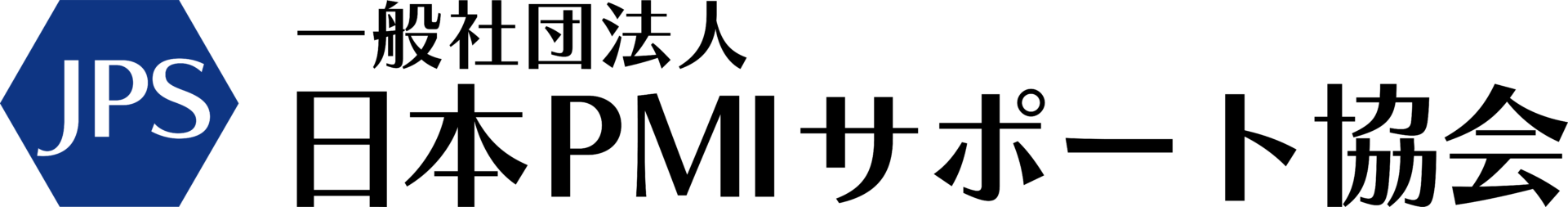はじめに
M&A後、PMI(統合プロセス)を自社で推進しようとしたものの、現場の抵抗や部門間の対立で全く進まない。かといって、大手コンサルティングファームに依頼したところ、提供されるのはどこかで使ったような紋切り型のフレームワークが高額で提供される。少し専門分野になれば別のコンサルへの依頼が必要となり、コミュニケーションコストも上昇。そんな八方塞がりになっていませんでしょうか。
私自身、経営企画責任者としてそうした状況に置かれた経験が幾度となくあります。そのPMIの進め方では、M&Aは単に「高価な買い物」で終わり、シナジー創出という本来の目的は永遠に達成されません。
本記事では、PMIがなぜ当事者だけでは難しいのか、M&Aを成功に導く「真のパートナー」の条件を提示します。
1. なぜPMIは当事者だけでは成功確率が低いのか?
M&Aの成立後、PMIを自社のプロジェクトチームだけで推進しようとする企業は少なくありません。しかし、その多くが深刻な壁に突き当たります。PMIには、内部の人間だけでは乗り越えるのが極めて困難な、3つの構造的な課題が存在するからです。
1-1. 「客観性」の欠如と内部の力学
当事者である社員は、良くも悪くも、既存の企業文化や人間関係、部門間の力学の中にいます。そのため、自社の問題を客観的に把握することが難しく、改革を進めようにも「あの部署には強く言えない」「この慣習は聖域だから」といった内部のしがらみに縛られてしまいます。これでは、本当にメスを入れるべき問題に踏み込めません。
1-2. 「感情的な対立」の罠
PMIは、既存の序列や業務プロセスに変化をもたらすため、必ず感情的な反発や抵抗を生みます。これまで同僚だった相手に、厳しい変革を要求し、その実行を管理することは、想像を絶するストレスを伴います。個人的な感情が絡むことで、本来解決すべき課題が、部門間、あるいは個人間の「感情的な対立」にすり替わってしまうのです。
1-3. 経験とノウハウの絶対的不足
ほとんどの企業にとって、大規模なM&AやPMIは、数年に一度あるかないかの非日常的なイベントです。そのため、社内にPMIを体系的に経験した人材はほぼ存在しません。過去の成功パターンや失敗事例といった「経験知」が不足したまま、手探りで進めるPMIは、羅針盤なくして大海原に乗り出すようなものであり、その成功確率は著しく低くなります。
2. 既存のコンサルティング支援の特徴
当事者だけでは難しい。その結論に至った企業が次に頼るのが、コンサルティングファームです。しかし、ここにも大きな落とし穴があります。特に、PMIという特殊な領域においては、量産型コンサルティングモデルそのものが、構造的な欠陥を抱えているケースが少なくないのです。
2-1. 「標準化モデル」と「個別性」の衝突
一定規模以上のコンサルティングファームのビジネスモデルは、成功事例を「標準化(テンプレート化)」し、それを多くの案件に適用することで収益性を高める構造になっています。しかし、前述の通り、PMIの前提条件は案件ごとに全てが異なります。「同じ統合案件など二つとない」のです。この個別性の高いPMIに対して、標準化されたテンプレートを適用しようとすること自体に、根本的な矛盾が生じます。
2-2. 「アソシエイト中心」の体制と「経験知」の不在
大手ファームでは、経験豊富なパートナーが契約を獲得し、実際の現場作業は若手のコンサルタントが担う、という体制が一般的です。しかし、PMIで最も重要な、人の感情が絡む複雑な問題を解決するには、ビジネスのフレームワークを使いこなす能力以上に、人生経験に裏打ちされた「人間力」や「胆力」が求められます。経験の浅い担当者では、百戦錬磨の現場社員の心を開き、動かすことはできません。
2-3. 大量生産モデルに基づく手離れの良さ優先
実際に、大手コンサルに依頼したものの「提供される資料は立派だが、熱量も現場感はさほどなく、淡白だった」という理由で、当協会に相談が持ち込まれるケースがあります。もしかすると大手コンサルにとっては数あるプロジェクトの一つに過ぎないかもしれません。しかし、当事者にとっては会社の未来を左右する一大事です。この「熱量」の差が、最終的な成果の差となって表れます。
3. PMI成功に導く「真のパートナー」3つの条件
当事者だけでも、既存のコンサルだけでもない。では、一体誰を頼るべきなのか。私たちは、M&Aを成功に導く「真のパートナー」には、3つの絶対条件があると考えています。そして、それこそが、私たち一般社団法人日本PMIサポート協会の存在意義そのものです。
3-1. 条件①:修羅場を越えた「実務家」であること
PMIの現場で本当に価値を持つのは、綺麗な理論ではありません。実際に事業会社の立場で、経営と現場の間で悩み、汗をかき、数々の修羅場を乗り越えてきた「実務家」としての経験です。私たちのパートナーは、全員がそうした経験を持つ専門家です。だからこそ、机上の空論ではない、血の通った支援が可能です。
3-2. 条件②:スケールを追わない「伴走型」であること
私たちは、事業規模の拡大や、手足となる若手コンサルを量産するビジネスモデルを追い求めません。なぜなら、それでは私たちが提供したい本質的な価値が薄まってしまうからです。また昨今はその手足としての機能は大部分、AIにて代替できます。一方で当協会は、経験豊富なパートナーが、最初の1on1から最終的な統合の完了まで、責任を持ってプロジェクトに寄り添い、共に走る「伴走型」の支援にコミットしています。
3-3. 条件③:PMIへの「愛情」と「情熱」があること
少し青臭く聞こえるかもしれませんが、私たちは、PMIという仕事が“好き”です。異なる文化が混じり合い、人が変わり、組織が新しい強さを手に入れる。そのダイナミックな変革の瞬間に立ち会い、従業員の目が輝くのを見ること。それこそが、私たちの仕事の醍醐味であり、情熱の源泉です。この当事者意識にも似た「情熱」こそが、私たちの支援の品質を支えています。
PMIは“非効率”だからこそ、パートナーの「質」が問われる
PMIは、当事者だけでは客観性を失い、大手コンサルの標準化モデルでは個別性に対応できない、極めて特殊な領域です。だからこそ、その成功には、中立的な立場から、個別具体的な課題にどこまでも寄り添う「第三者」の存在が不可欠となります。そして、そのパートナーは、豊富な実務経験と、最後まで伴走する覚悟、そして何よりプロジェクトへの情熱を兼ね備えていなければなりません。
標準化や効率化では決して届かない、人間的で泥臭い領域に、真正面から取り組む。それが、私たちが存在する理由です。もし貴社が、M&Aを真の成功へと導くための本物のパートナーを探しているのなら、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
→ 無料相談・お問い合わせはこちらから
https://pmi-support.jp/contact/
執筆:後藤俊輔
一般社団法人日本PMIサポート協会 代表理事
SynStream株式会社 代表取締役
ローム株式会社、オムロン株式会社、株式会社YUSHINにて、法務担当、M&A/経営企画責任者、生産管理責任者等に従事。
副業で経営コンサルティング経験を重ねた後、2023年11月に独立。SynStream株式会社代表として、大手企業のM&Aアライアンス、PMIのプロジェクト支援、中小・ベンチャー企業の経営幹部代行に従事。
2025年5月に一般社団法人日本PMIサポート協会を設立し、M&A後の統合支援・人材育成に特化した事業を本格始動。
法務博士、MBA保有、プロコーチ資格保有