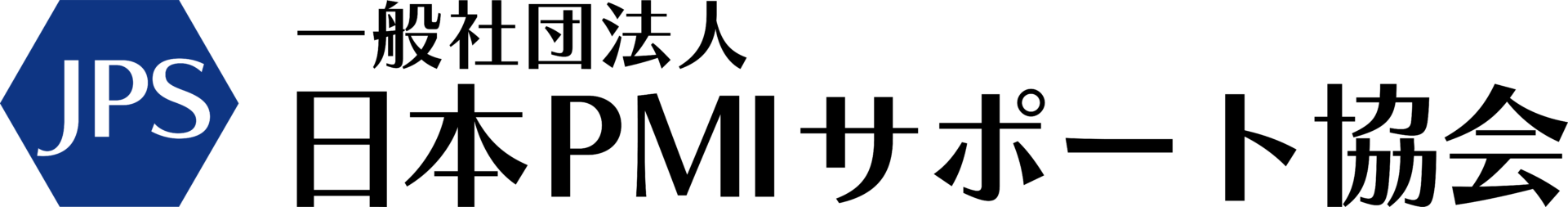日々新聞を賑わすM&A報道。企業買収といえば「誰がどこを買ったか」が注目されがちです。しかし、買収の本当の勝負はその後に訪れます。買った側と買われた側が、一つの組織として再出発する過程、つまりPMI(Post Merger Integration)こそが、M&Aの成否を左右します。
日本電産・永守会長の「買収は2割、残りの8割はPMI」という言葉がその重要性を端的に表しています。
では、なぜPMIはここまで重要で、難しいのか。当協会の考えを記します。
PMIとは何か?M&Aの“その後”に訪れる統合プロセス
PMIとは、M&A後に行われる組織・人・制度・文化・業務プロセスの統合活動です。買収の「契約」はゴールではなく、実はスタート地点。その後の統合作業を通じて、初めてシナジー(相乗効果)や成長が実現されます。この事は言わば当たり前の事なのですが、多くの企業が躓くのが現実です。XXX調べによると、
なぜ多くの企業がPMIでつまずくのか?
PMIは「正解のないマネジメント」だからです。
-
- 被買収企業の文化や人間関係に踏み込む必要がある
-
- 通常業務と並行で進めねばならない
-
- 各部門の巻き込み、抵抗の緩和が必要
こうした“泥臭いけれど大事なこと”に本腰を入れられる企業は、実は少数派です。
ドラマの主役は「買収」だが、成果はPMIにしか生まれない
買収は「ドラマチック」で外部にアピールしやすく、メディアにも取り上げられます。
しかし実際に企業価値を高めるのは、日々の地道な統合活動。誰にも注目されず、混乱も多く、成果もすぐに見えない。けれどここに本質がある。
PMIの失敗がもたらす“代償”とは?
PMIが失敗すると、以下のような問題が起きます。
-
- キーパーソンの離脱
-
- 現場の士気低下
-
- 恒常的業績不振によるキャッシュの流出
つまり、買収にかけた数十億円〜数百億円がそれだけに止まらず、さらなる出血を伴う場合もあるのです。
PMIは“ToDo消化”ではなく“変革のデザイン”
PMIは単なるToDoの消化ではありません。
異なる文化・人材・組織を一つにし、新たな組織を形づくる──「変革のデザイン」です。
だからこそ、戦略眼と現場感覚、双方を持つ存在が伴走する必要があるのです。
まとめ:PMIを制する者が、買収を制する
PMIは「買った会社を活かしきる」ための最も重要なステージです。
ここをおろそかにすれば、どれほど立派な買収戦略も絵に描いた餅で終わります。
当協会は、この“見えづらく・誰もやりたがらない”領域こそ、企業の未来を決める本質だと考え、PMIに専門特化しています。
次回は、なぜ私がPMI支援に特化することを決めたのか、その背景についてお話します。